

さて、第2回目は「マスク」に関するお話です。本編開始から20分ほど経過したところのシーンで、マスクがポケットの中から取り出したのが風船ではなく使用済みのコンドームだった、というジョークを理解できたのは中学生になってからのことでした……どうでもいい話ですね、すみません。
マスクは1994年公開、主演はジム・キャリーとキャメロン・ディアスです。本作についてさらに詳しく知りたいという方はWikipediaをご覧ください。
ここから先は、お時間に余裕のある方のみ、お読みください。物語は僕が5歳だった1999年1月頃のことです。
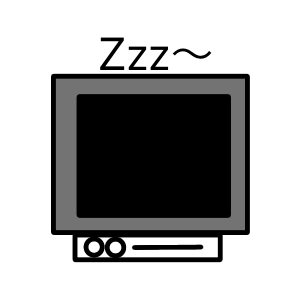
急にテレビが暗くなった。
事態を把握するまでには数秒の間があった。停電か、と思った。静寂の中に、ブラウン管の駆動音の名残だけが聞こえる。僕は肘枕をほどいて上体を起こした。
時刻は正午過ぎである。南向きの窓からは激しい日光が降り注いでいた。頭上の照明はそのためにつけていなかった。したがって部屋の明暗からは、停電か否かを瞬時に判断することができない。しかしよく見ると、ビデオデッキの電源ランプは稼働中を示す緑色に光っている。すると、やはり停電ではないようだ。
そこに、背後から殴るような母の声が、僕の脳天めがけて飛んできた。
「いい加減、その映画やめなさいよ」
振り返ると、まるで色を抜いたような表情で母は僕を見ている。そして母の手には、しっかりとテレビのリモコンが握りしめられていた。なるほど、母がテレビを強制終了したわけだ。さすがの母も、ターミネーター2(以下、T2)には嫌気がさしたようである。
5歳の僕はある日、テレビ放映を録画したT2のビデオを親父から受け取った。これに衝撃を受けた僕は、以来ずっとT2を観ていた。このごろは、僕があまりにT2ばかり観るので、当該作品を提供した張本人である親父も辟易していた。ただし親父は、金がかからなければ好きなだけ観てもらって構わないさ、という寛容的な心を持ち合わせていた。僕が親父の前で自由に行き来できたのも、こうした通行手形を事前に交付されていたためである。
ところが母の場合、親父のように、おいそれと手形を発行できない、個人的な事情があった。
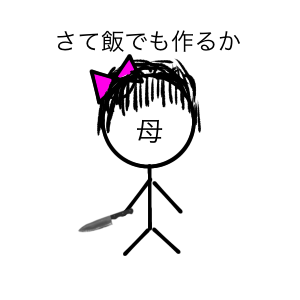
母は昭和30年、大分県の田舎に生まれた。貧しい家庭だったこともあり、紆余曲折あって東京に上京したのが15歳の頃だった。親父とはそれからしばらくして出会い、22歳の時に結婚。先に姉と兄を産んだのち、母が38歳の頃、僕が産まれた。当時の平均出産年齢が26歳前後であることを考えると、かなりの高齢出産である。
母は結婚当初から専業主婦だった。いつも家には母がいた。親類は近くに誰もおらず、母一人でこの家の全てをこなす必要があった。とうの昔に体力的な盛りを終えた母の身体には、家事全般はすこぶるこたえるようで、居間でついうたた寝をする母の姿をよく見かけたものである。
そんな母の唯一の娯楽がテレビだった。特に連続ドラマや2時間ドラマを好んでよく観ていた。何故ドラマが好きなのか、母に尋ねると、毎回違った内容で飽きが来ないから良い、との見解を示した。これがT2しか観ない僕の感覚を、母が理解できない最大の要因である。とはいえ、当時の僕はたしかに度が過ぎていた。T2を狂ったように観ていた。したがって、母の異議申立てに対し、強い反論をもって対峙できるほど、僕は律した人間ではなかった。
そこで、僕は新たな作品を仕入れるべく、その頃毎日のように放送されていた夜のロードショー枠をビデオに録画しておくことを考えた。そうすれば、母のストレスをいくらか軽減出来るだろうし、子供はとっとと寝ろという親の意向にも沿えるので、僕にしてはなかなか良い落とし所を見つけたものだと満足していた。
ところが、その計画を知った母が、予想外にも難色を示した。要するに、夜飯を食い終わった後は、皿を洗うだの風呂を沸かすだの寝室を整えるだの、あるいは親父との時間を大事にしたいだの、自分にはいくらでも仕事があって、楽しみにしている2時間ドラマをリアルタイムで観れないから、これを録画しておき、昼間の空いた時間を使ってゆっくり観たい、というのが母の主張であった。
不運にも家にはテレビが一台しかなかった。つまり母の希望通りにシナリオが展開されると、21時台からのロードショーが2時間ドラマとバッティングし、その結果新しい映画を手に入れることができず、僕は一生T2の沼から抜け出せなくなる、という落ちだ。
これは非常に困る。かといって、中途半端に反対したりして、じゃあお前が家事を代行してくれるのか、と返されてしまえば、ことである。やはりこういう局面においては、圧倒的に大人が有利である。だが、若干5歳の僕が救いを求めるところも結局は大人であり、とどのつまりそれは親父なのだが、お母さんも家のことを頑張っているんだから、たまには息抜きもさせてあげないとな、ともっぱら母に加勢する。ドラマの録画予約は、いつも親父が担当していたので、たまには僕のために不義を働かせる、つまり、ドラマを録画するふりをして、実際は映画を録画することはできないか、と裏で交渉してみるも、馬鹿野郎、何度か俺は録画操作を誤って、大変怒られたことがあるんだ、その恐ろしさを知っていながら、罪を犯せというのか……親父がささやくその声は、背後に迫る母の影に震えていた。
僕はさじを投げるようにして、二階の寝室へ向かう。そうして否応なしに階下から聞こえる、大人たちの楽しげな声が、僕を何だか悲しくさせる。日によっては、ロンやらチーやらポンなどといった掛け声が、盛大に響いてくる。
いくらでも仕事はあると母は言ったが、談笑や麻雀が、仕事だというのか。こんな不条理が、まかり通っていいものか……しかし一方で、親父の言う、母も家のことを一生懸命に云々という趣旨の言葉が、実際その姿を普段から目の当たりにしている僕には、ことのほか重くのしかかっていて、文句の一つも言いづらい雰囲気である。こうしてどっちつかずのまま、ふらふら彷徨っているうちに、大体が気づくと寝てしまって、朝になる頃には、すっかりこの問題を忘れているのである。
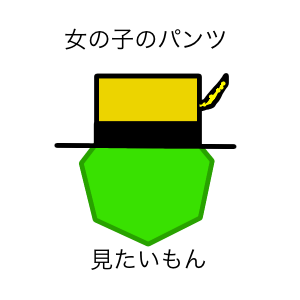
こうした経緯を辿った上での、T2強制終了事件だった。
「いい加減、その映画やめなさいよ」
母はテレビを消したあとも、しばらくぶつぶつ言っている。ここは一旦退いた方が、物事を穏便に済ませることができるかもしれない。
「お母さんにもそろそろテレビ観させてね」
そう言われ、昼飯の焼きそばをくちゃくちゃ食いながら、僕は母と並んで、録画しておいた十津川警部のうんちゃらかんちゃらとかいう2時間ドラマに付き合った。ところが開始10分ほどで、眠気が襲ってきた。
それにしたって、T2と比べてしまうと、どれもこれも陳腐である。カーチェイスや銃撃戦を十津川警部に求めたところで、どうにもならないことは理解している。しかしどうしてこう2時間ドラマというやつは、こんなに退屈なんだろうか。謎解きはいいから、せめてビルを一棟爆破させるくらいの迫力は欲しいものである。
すると、この不平不満が伝わったのか、突然ビデオの調子が狂い出す。ノイズが走り、しまいには画面の半分以上がまともに観れなくなった。
「ねぇ、クリーニングしてくれない?」
焼きそばを頬張り、息の詰まるような声で、母が指示を出す。まったく、いつだって大人は横着だ。自分で探せばいいものを、子供を便利な道具のように扱う。嫌々ながら、僕は収納棚に目をやって、クリーニング用ビデオを探す。けれど、何故か見当たらない。別の場所に放っておいてしまったのだろうか。棚に入りきらないビデオが、テレビ台の脇に積んである。だがそこにも無い。廃棄予定の不良ビデオを詰め込んだ大きめの紙袋があって、一応そこも確認する。やはり無い。テレビ台の後ろを覗くと、埃に埋まったビデオが二、三本転がっていた。それを見て、さすがにあれは違うか、と呟いた。それを母は聞き逃さなかった。
「ちょっとあんた、そんなところにもビデオがあるわけ?」
「うん。何本か落ちてる」
「どうやったらそんなところに落ちるのよ」
「何かの拍子でテレビの上に置いたまま、地震でも来たんじゃないかな。そうじゃなきゃ、向こう側には落ちないだろ」
「何でもいいけど、そのままにしないでさ、ちゃんと回収しなさいよ」
……これは面倒なことになった。下手すると、掃除機をかけろなどと言い出しかねない。
しかし母の顔から、例の家事による疲労が滲みでている。その眼で、僕をじっと見てくる。急に同情心が芽生え出した僕は、そそくさとテレビ台をずらし、埃の中に手を入れた。ここもまた、素直に働いたほうが身のためである。そして、やつと出会った。
「あら、そんなところにあったのね」
偶然手に取ったビデオに『金曜ロードショー マスク』と書いてある。
「昔、ドラマの録画をお父さんにお願いしたら、間違って映画を録画しちゃった時があって、そのビデオ、たぶんそうでしょう」
点だったものが線に変わった。親父が言っていたのは、このことか。しかし親父も親切じゃない。わざわざタイトルを付すくらいだから、誤って録画したそれが映画だったことも、実は知っていたかもしれない。断片的な記憶でも、少しは教えてくれたっていいような気がする。
いずれにせよ、この家にT2以外の映画を収めたビデオが存在していたとは、まさに世紀の大発見である。その上、この映画に対する母の好意的な態度にも驚いた。マスクは面白い、何回見ても面白い、というのだ。
それならばと、母の了承の上、急遽マスクの上映会を開催することになった。
……そう、僕はこれが欲しかったのだ。
スラップスティックの体裁と、SFXによる演出が、主演のジム・キャリーと相まって、完璧なコメディを作り出していた。ココ・ボンゴでのステージシーンにおけるキャメロン・ディアスの色気には、5歳児の僕の身体でも大いに反応した。それから、映像的なリズムに気持ちよく乗せてくれる、スイングをベースとした楽曲と、それを使うタイミングの良さ。なにより笑った。心の底から笑った。それは母も同じだった。
結局、僕と母との間で勃発する21時台の録画戦争に僕は勝つことができなかった。けれども以前ほど、僕は苦虫を噛みつぶすような思いをしなくなった。マスクの存在が、僕に余裕を与えていたのである。なにより最近では、ビデオデッキの操作方法を親父に教わって、母の観たい番組を僕が録画してやるまでになった。そう、いつだって僕は、ビデオデッキを不正に操作できる地位にいたのである。しかし当面の間は、母の娯楽を収集することに精を出そうかと思う。強力な武器は私利私欲のために使うと、手痛いしっぺ返しを食らうのが世の常であるから。
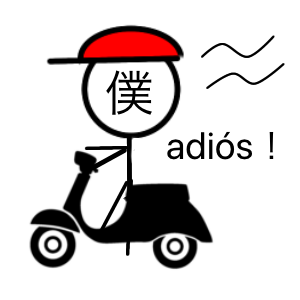
僕が映画で初めて笑った作品はマスクである
僕が映画で初めて笑った作品はマスクである